料金をどう設定したら良いのか?【その②】値決めの考え方(サービス業編)

税理士のあさがおです。
前回の続きで、テーマは、値決め。
今回はサービス業に絞って考えていきます。
【サービス業の例】
✅キャリア・コンサルタントなどのカウンセリング業
✅弁護士・税理士などの士業
✅ホームページ制作などのIT業種
■サービス業はなぜ値決めが難しいのか?「仕入商品」との違いを解説
「仕入」という目に見えるモノがある場合、相場が見えることは多いです。
大根1本の金額って、よほどこだわっているものを除けば、
スーパーごとでそこまで変わることはないですからね。
対して
サービス業は、人が行う目に見えない役務の提供です。
例えば
カウンセリング1つとっても、
行う人が違うわけですから、
AさんとBさんが行うものは全く異なります。
結果、
値決めも異なってくるといったことが
当たり前に起きてきます。
つまり、
相場が見えづらく、値決めをしにくい
という問題があります。

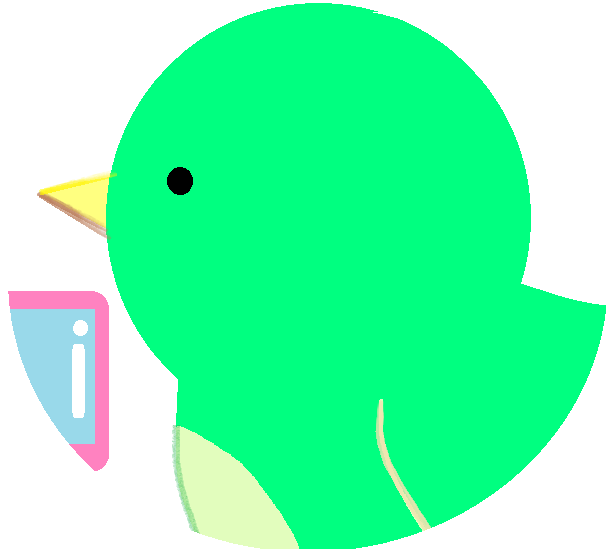
分かります!
私のホームページ制作の場合。
◉フリーランスとWeb制作会社、
◉ワードプレスと静的HTMLだけで作る方法、
◉内容のコンサルの有無
など…
事業規模・やり方・使うツール
がそれぞれ違うので、
どこに依頼するかで
値段がぜんぜん違うということが
多々あります!
■「委託?請負?」まずはここから。
では、サービス業の値決めは、どこに主軸を置いて考えれば良いのでしょうか?
2つの方法をご紹介します。
①時給の考え方(タイムチャージ方式)~委託

一つの考え方としては、
時給のように計算する方法がありますね。
タイムチャージ方式とも言ったりしますが、
作業の1時間(1日)当たりいくらを請求するといったやり方です。
労力がかかればそれだけ時間がかかりますから、
それだけ請求額も増えるといった形です。
この方法、いくつかのサービス業では、よく使われています。
法律相談を行う弁護士さんでも良く聞きますし、
建設業で働く外注さんにも、人工(にんく)計算としてよく出てきます。
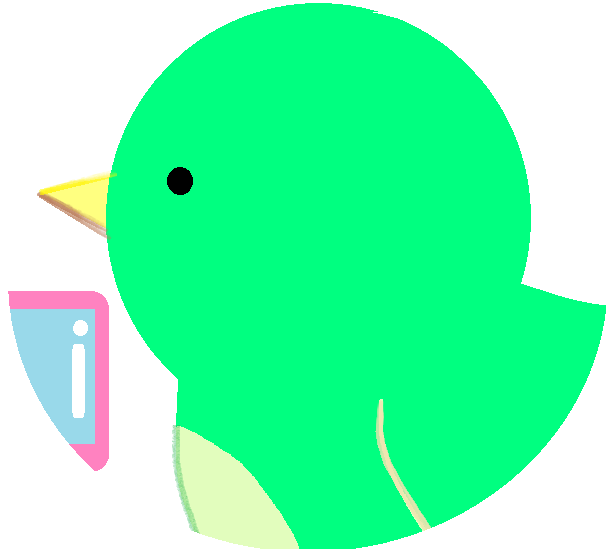
確かに私も独立前、
時給〇円(百~千円単位)でパートで働いていたので、
「時給〇円×働いた時間」というのは
感覚としては分かりやすいです。
一方、
ITサービスやHP制作は、
単価が大きい事業(万単位)で、
「ひとつの仕事で〇円」という単位が一般的です。

まさにそこがポイントです。
同じサービス業でも、
「業務をやること」で値決めする方法(≒委託)
「成果物を完成させること」で値決めする方法(≒請負)
という2種類があるということですね。
②成果物の完成~請負

委託と請負を、
具体例で見てみましょうか。
A2Kさんの業務には
・ホームページ制作
・ITトラブル対応
がありましたよね。
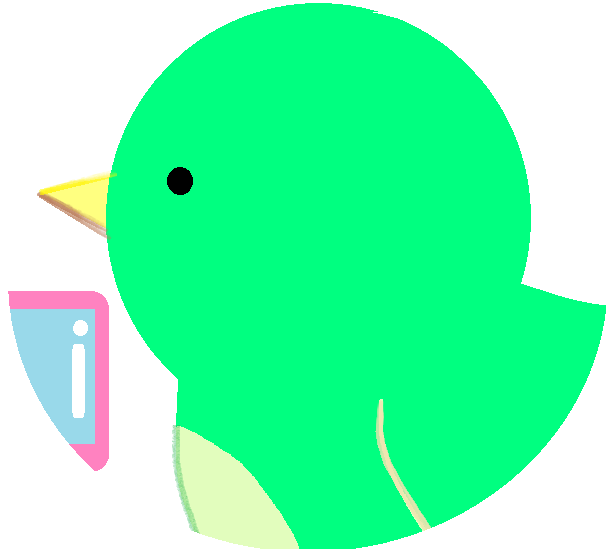
はい、あります!
一般的に、
ホームページ制作の場合、
完成したホームページという成果物をお客さんは欲しがっているので
後者(≒請負)ですね。
一方で、
保守やトラブル対応などは
何かを完成させるのではなく
トラブルの状態を見たり、場合によっては修正するなどの作業なので、
前者のタイムチャージ方式が合うと言えます。
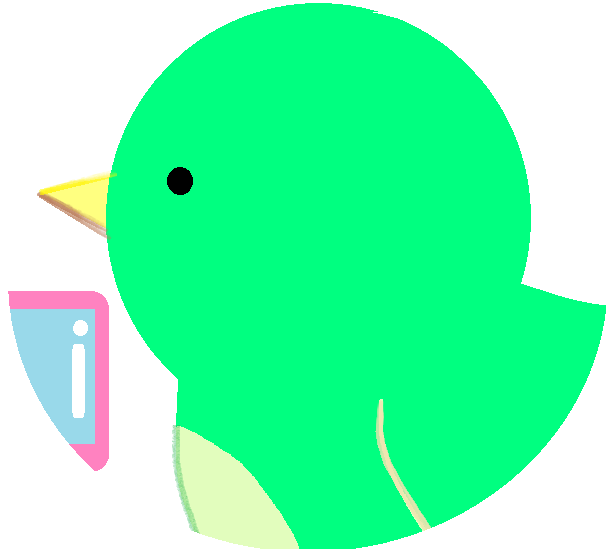
なるほど…
確かに
「作業の内容」や「成果物の有無」
が違いますね。
トラブル対応も、
もしそのまま様子見になれば、
調査結果の報告で終わりですし。

そうなんです。
これらは
提供するサービスの内容によって違いが出ますので、
それに合う方を選ぶのがコツだと思います。
値決めの二つの方向性(サービス業の場合)
①「業務をやること」で値決めする方法(タイムチャージ方式)
②「成果物を完成させること」で値決めする方法
■値決めの具体的なやり方(サービス業編)

では、
「具体的にいくらに設定すればいいの?」
について、考えていきましょう。
①「業務をやること」で値決めする方法(タイムチャージ方式)
こちらの場合、「1時間当たりいくら」という形での設定が必要です。
時給の設定ですね。
アルバイトの時給と比べると3,000円でも高く感じますが、
普通は5,000円~数万円の間で設定するサービスが多いように思います。
ポイントは、サービスを切り分けて細分化することだと思います。
業務の難易度や責任の度合いによって、当然ながら金額は変わります。
A業務:1時間 5,500円
B業務:1時間 7,700円
C業務:1時間 11,000円
このように切り分けて、分けるとお客様側に分かりやすく選んで頂けます。
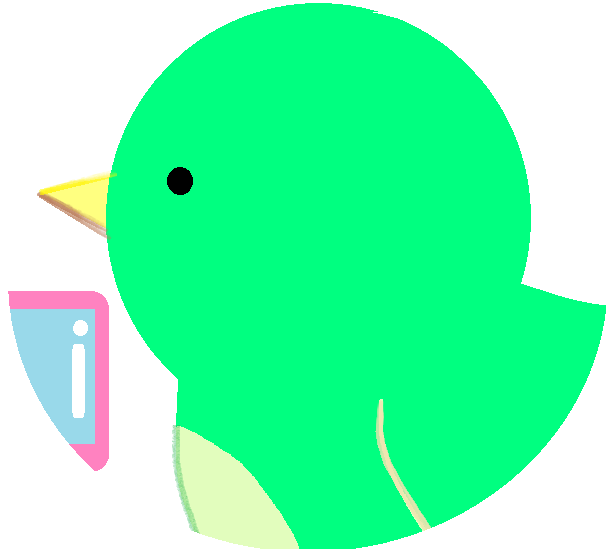
私も
ITコンサルティング業務については、
このようなやり方をとってます!
2時間以上は少し下げたり、色々とアレンジもできますよね。

そうですね!
あとは、創業時だけは少し安く設定して数をこなしつつ、
それで増えた実績をもとに金額を上げていく方法も良いですね。
②「成果物を完成させること」で値決めする方法
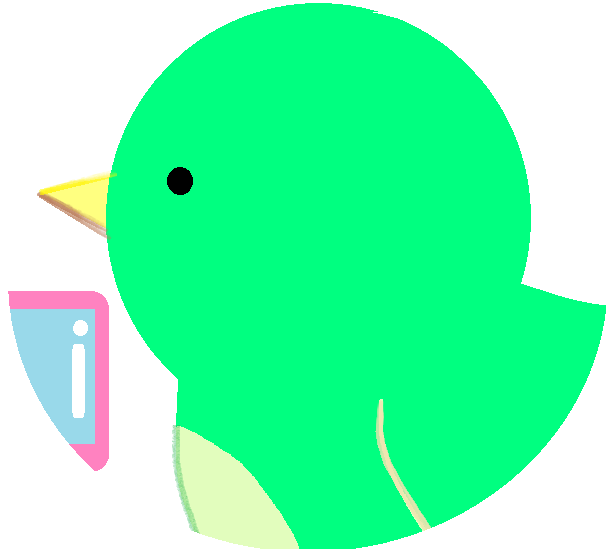
先ほどのタイムチャージ方式と比べると、
やっぱりこっちは値決めが難しいです。
そもそも1件単位なので金額が大きくなりがちですし、
相手の要望や対応で金額も変わるので、
「HP制作 1件〇円」と提示しにくい問題があります。
おっしゃる通りで、こちらの値決めをしていくのはとても難しいです。
ただ逆に言えば、お客様側でも値決めの判断が難しいわけです。
どのような作業がどの程度あるのかが見えないから、
料金が高いか低いかを判断することができないわけです。
なので、こちらもポイントは、サービスを切り分けて細分化することだと思います。
参考:サービスの細分化の例

具体例として、
わたしとA2Kさんのサービスを
細分化してみましょうか。
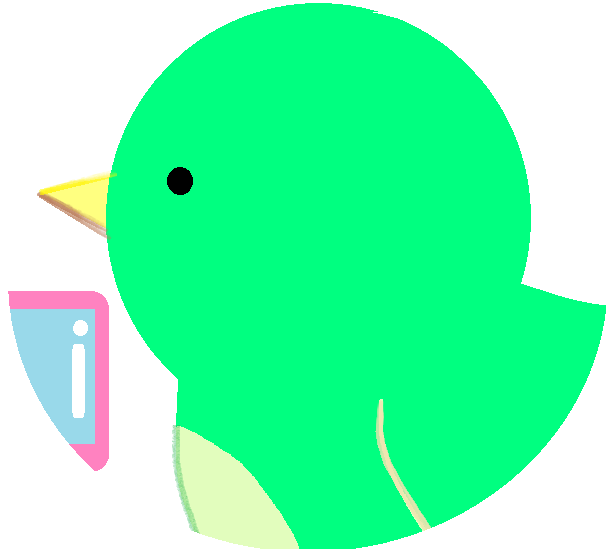
はい!では、
ホームページの新規制作やリニューアル時
を例としますね。
- コンセプト設計(お客様に伝えたいことなどをまとめる)
- サイト設計(①をHPの構成に反映)
- トップページ3スクロール見本作成(一番目につきやすいところを先に作り込み)
- トップページ見本作成
- その他のページ作成
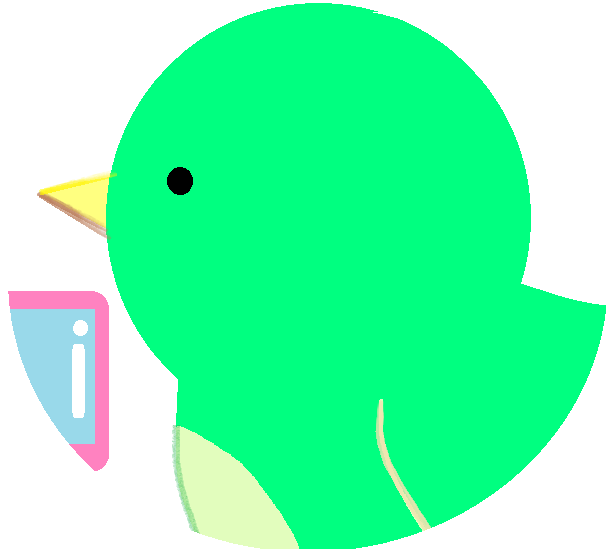
こんな感じですね。
起業当初は、こんな風にわかりやすく細分化できてなくて…。
これが出来たの、1年くらい前なんです。
でも、これが出来てから、
・一番価値があるのはどの工程か
・だから、この金額に設定している
という説明がしやすくなりました。
それに伴い、
値決めのあやふやさが
減ってきたように思います。

そうだと思います。
サービス業は
お客様にとって
やることが「見えにくい」
というのがポイントですかね。
なので、
「見える化」するために
書き出したり細分化したりするのが
おすすめなんです。
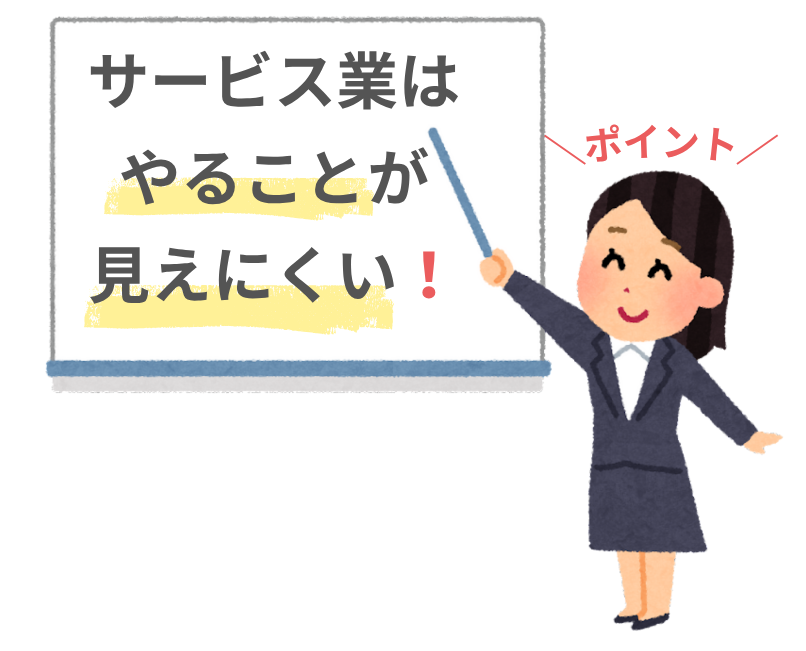

私の税理士顧問業についても、ご紹介させて下さい。
業務と値決めが月→年単位なので、
行う業務内容があやふやになりがちです。
なので
関与当初は年間スケジュールを提示して、
・こういう形で
・いつ頃に何をしていきます
と提示するようにしています。


そうでないとお客様は
それぞれの作業について、
高いのか安いのか判断つかないですからね。
逆に
やることを提示することで、
お客様側で納得して選んで頂けますし、
自分が本当に届けたい価値も洗練されていくように思います。
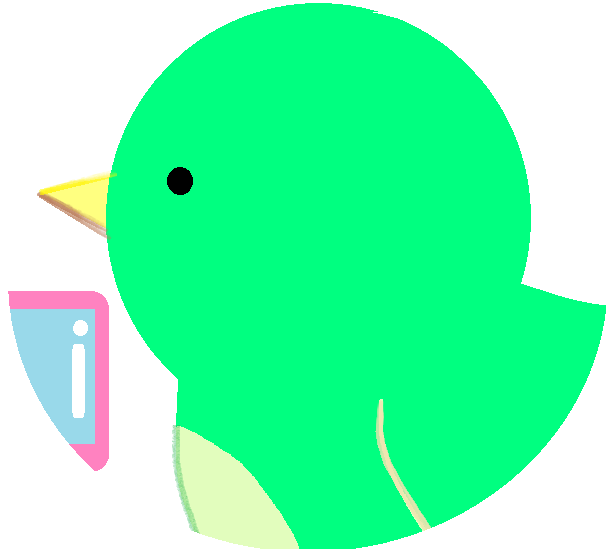
そうですよね。
わたしも起業5年目にして、これを掴めてきた感覚があります!
■サービス業の値決め~まとめ
サービス業は、そもそもやることが見えにくいので、
それを見えるようにするだけでも、他の業者と差別化になったりします。
業界内では当たり前になっていても、
意外とお客様側では相場が分からないということも多いように思います。
それでも難しい場合は、
「〇円~」「詳しくはお見積り」とすれば良いのだと思います。
値決めは、他人と比べてどうこうするものではなく、
自分とお客様の間で合意して一緒に決めるもの。
その観点を忘れずに値決めを考えていただけたらと思います。
値決めの方法(サービス業の場合)
・サービスの内容を「業務をやること」と「成果物を完成させること」で分ける。
・サービスをいくつか切り分けて、細分化してお客様に提示する。
・それでも難しい場合はお見積りとし、お客様と一緒に決める。
この記事を書いた人

あさがお税理士事務所 代表税理士 伊藤貴文
税理士 / 栃木出身 / 埼玉在住 / 東京勤務 / 3児の父
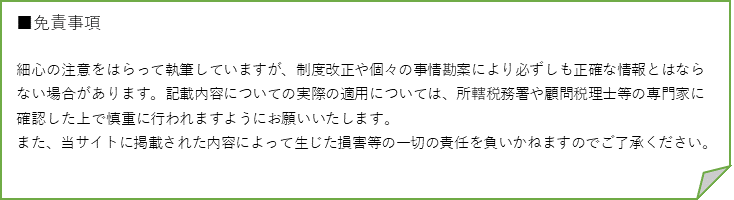
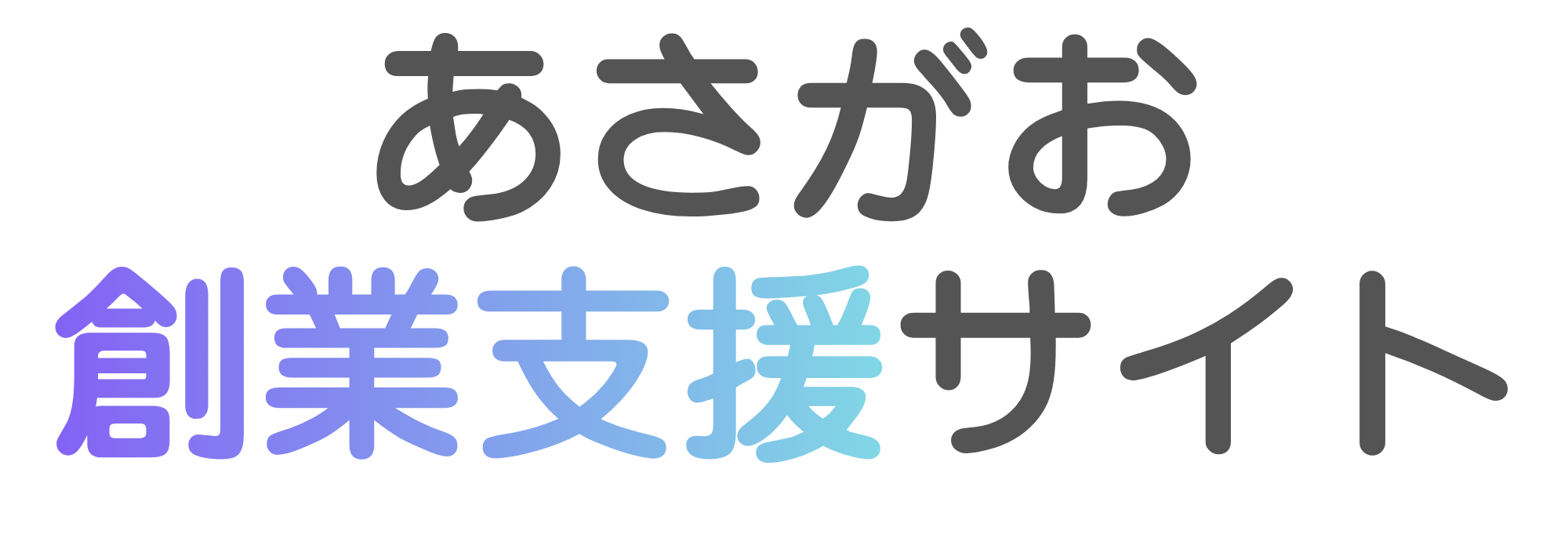
.jpg)