料金をどう設定したら良いのか?【その①】値決めの考え方(仕入れがある業種編)

税理士のあさがおです。
最近の物価高の影響で、スーパーから飲食店までどこも値上げラッシュですね。
我々事業主も例外ではなく、様々なコストが値上がりしている中、
料金を変えていかないといけないと考えている方は多いんじゃないでしょうか。
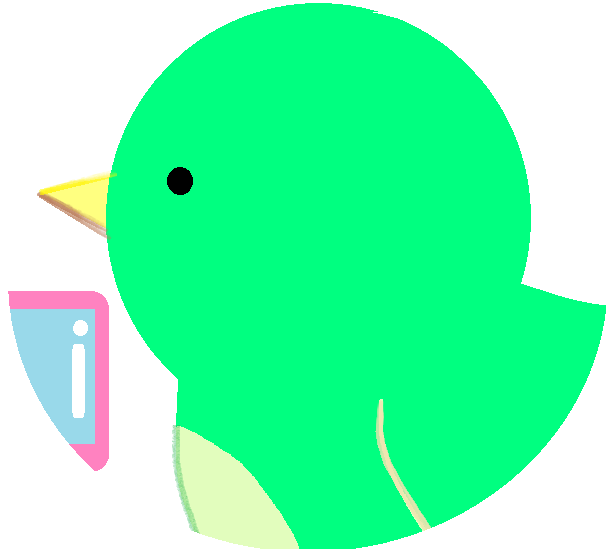
たしかに、
「値上げしたんだ!」の報告、多いですよね…。
自分のサービスの料金はどうする?
と考えることも、時々ありました。
ところがこの値決めの話、意外にもちゃんと考えたことがないという事業主の方は多いんじゃないでしょうか。
なんとなく同業者の相場を見て、『うちならこれくらいかなぁ?』と。
特にサービス業などの仕入の原価がない業種は、より難しかったりします。
今回はそんな地味だけど大切な値決めについて、考えてみたいと思います。
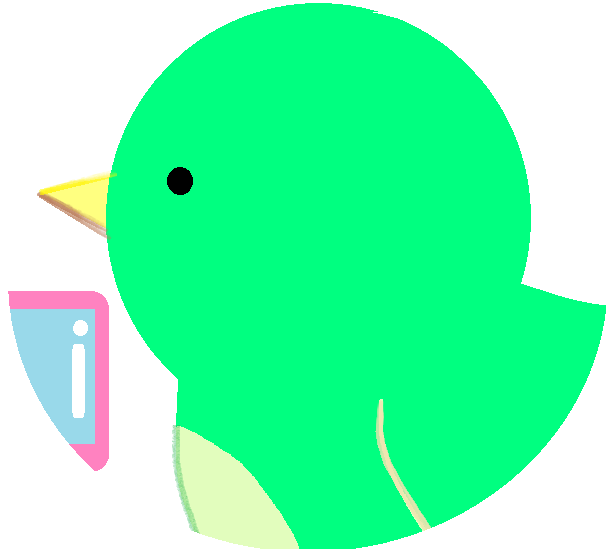
✅同業者と同じくらいの金額で…
✅よくわからないからこれくらいで!
という感じで値決めしている人(=わたし💦)に
役立つ内容になってます!
目次
■値決めの二つの方法
値決めのやり方には、大きく分けて二つの方向性があるように思います。
値決めの二つの方向性
①自分(自社)が欲しい金額を設定する方法
②相手(顧客)が欲しい金額で設定する方法
①自分(自社)が欲しい金額を設定する方法
こちらは、自分がこの商品・サービスを売るにはこれくらい欲しいという視点で料金を決める方法です。
”野菜を70円で仕入れた八百屋さんが30円の利益を乗せて100円で売る”
このように自分が必要な儲けの金額やパーセンテージを決められる良さがある方法です。
これはあくまで自分(自社)での都合で値決めする方法だと言えます。
②相手(顧客)が欲しい金額で設定する方法
先程の自分都合での値決めは、売り先である顧客の状況を考慮していません。
もう一つの方法は、逆に顧客側の立場に立って値決めをする方法です。
つまり、顧客がいくらなら欲しい・買いたいと思えるか?という視点で料金を決める方法になります。
顧客側の立場に立って値決めしますので、顧客側の納得感は得られやすい決め方にはなります。
ただ、先程とは逆に、自分が必要な儲けの金額やパーセンテージを決められず、
儲けを確保できない可能性がある方法だとも言えます。
* * *
まとめると、これら二つの値決め方法は、それぞれにメリット・デメリットがあります。
どちらが正解というわけではなく、
自分(自社)と相手(顧客)どちらの要素も織り込んで値決めをする必要があるということです。
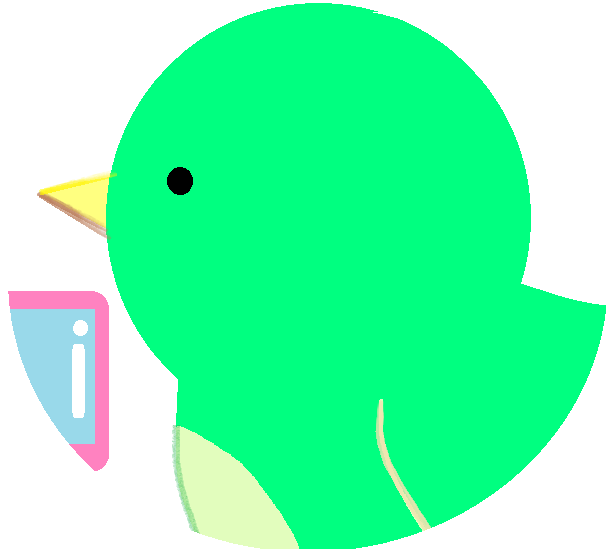
うんうん、考え方はよく分かりました!
ただ、具体的にどうやって決めていくのかは難しそうですね...

たしかにそうですね。
仕入値や顧客の需要も、日々変動するものですし。
決め方について、もう少し具体的に考えてみましょうか。
■値決めの具体的なやり方
①自分(自社)が欲しい金額を設定する方法
”野菜を70円で仕入れた八百屋さんが30円の利益を乗せて100円で売る” という例を先程出しました。
これは、会計上はこのように表現されます。
”野菜を70円で仕入れた八百屋さんが30円の利益を乗せて100円で売る”
●原価率70%(=売値100円÷仕入値70円)
●粗利益率30%(=粗利益30円÷売値100円)
この原価率は低ければ低いほど、粗利益率は高ければ高いほど良いのは間違いありませんが、
そうなると徐々に売れにくくなってきますので、バランスが重要です。
この原価率は、業種によって異なります。
例えば、卸売業や小売業など仕入れたものをそのまま売るような業種の場合、
そもそもの仕入値が割高であまり価値を乗せられませんので、それほど利益は乗せられないですよね。
逆に、製造業や飲食業など仕入れたものを加工して売るような業種の場合は、
手を加える過程に価値がありますので、利益はそれなりに乗せられます。
例えば、飲食店を例に出すと、食べ物とお酒どちらをメインにするかにもよりますが、
一般的には原価率30~40%(粗利益率60~70%)となる場合が多いと思います。
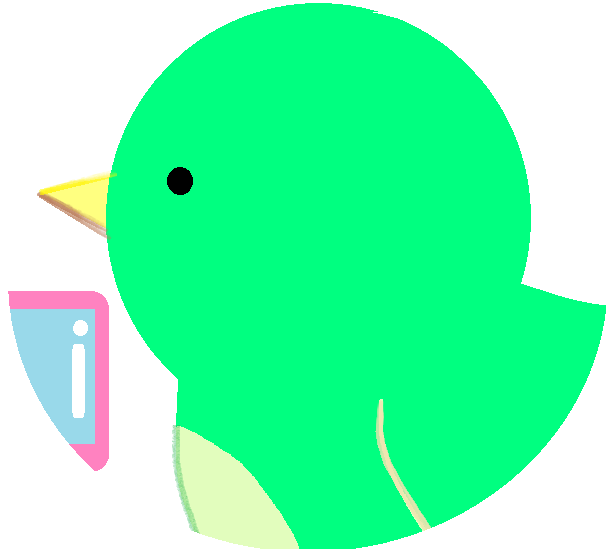
ということは…
1,000円のランチをカフェで食べる場合、
原価率40%なら、
400円が食材・調味料などの原価。
600円が利益ってことですね。
この利益を積み上げていって、
人件費や家賃を支払っているんですね!
これらはどのような業種でどのような商品を扱うかによって異なります。
ご自身のビジネスの原価率を検索してみて、自分がどの位置にいるかを確認してみましょう。
もし自社の原価率が平均より高く、原価率を下げる余地がない場合、
原価率が適正になるまで、売値を上げないといけないことが見えてきます。
参考にしつつ、自分(自社)が欲しい利益の額や%を設定して値決めをすると良いでしょう。

以上は、あくまで仕入れがある業種の話です。
サービス業のような仕入れがない業種は、
次回お話できればと思います。
②相手(顧客)が欲しい金額で設定する方法
一方の顧客がいくらなら欲しい・買いたいと思えるか?という視点。
顧客がいくらで欲しいかは、そのもの自体の価値だけでなく、
その顧客の置かれている状況や欲求の強さ、気分や感情などによっても左右されるという特性があります。

・近所の自動販売機で買う100円のコーラ
・お洒落なレストランで頼む500円のコーラ
どちらも味は同じですが、金額の違いは受け入れられていますよね。
他にも、例えばヴィンテージなどの一点物は、その希少性で金額が上下したりします。
つまり、扱う商品やサービスによって売値が変わるということです。
これは顧客側にしか答えがない世界になってきますから、
『顧客が許容と満足ができる最大の価格』がベストな値決めとなります。
あなたの商品やサービスを顧客が欲しいと思う価格ですから、
先程とは異なり、業界平均などと比べても意味がありません。
あなたの顧客の心の中に答えがある話ですので、
それを実現するためには、何よりも顧客とのコミュニケーションが重要です。
顧客が何を欲しているのか、どのような購買行動を取るのかを通じて、
それに最も合った金額で料金を設定することが重要です。
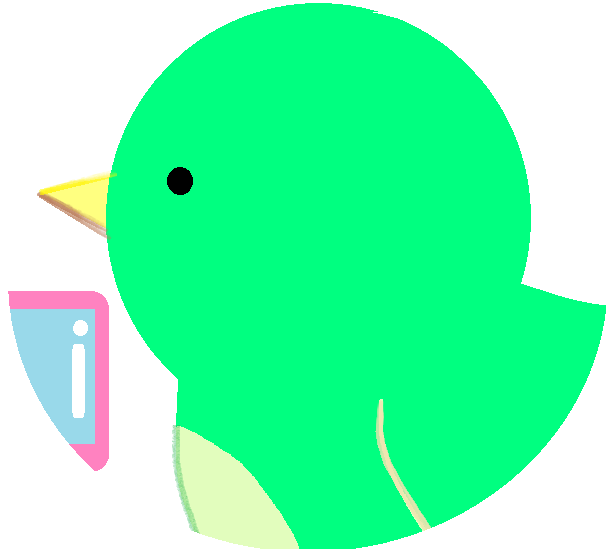
一見、
「売り手が有利」な話に見えますが、
違いますよね。
あくまで
「お客さま」にも「自分」にも
ベストな価格を探さないと!
ですね。
* * *
まとめると、このような結論になります。
値決めの方法
・まずは適正な利益率(原価率)を意識して、自分にとって必要な儲けの出る売値を探す。
・次に実際の顧客とのコミュニケーションを通じて、相手にとってちょうど良い売値を探す。
・それら売値の間を取って、自分(自社)と相手(顧客)にとってのベストな売値を決める。

次回、サービス業の値決めの方法について、
より掘り下げて考えていきたいと思います!
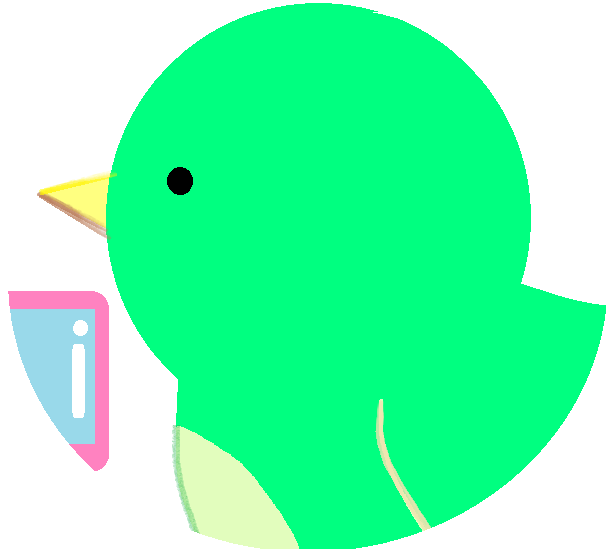
サービス業代表として、楽しみにしてます♪
この記事を書いた人

あさがお税理士事務所 代表税理士 伊藤貴文
税理士 / 栃木出身 / 埼玉在住 / 東京勤務 / 3児の父
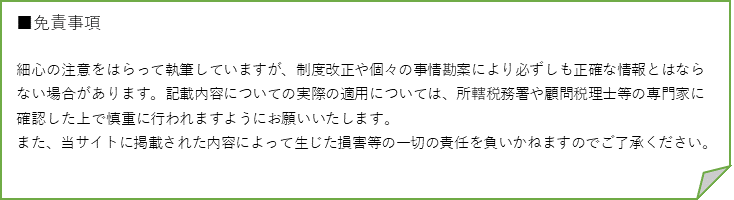
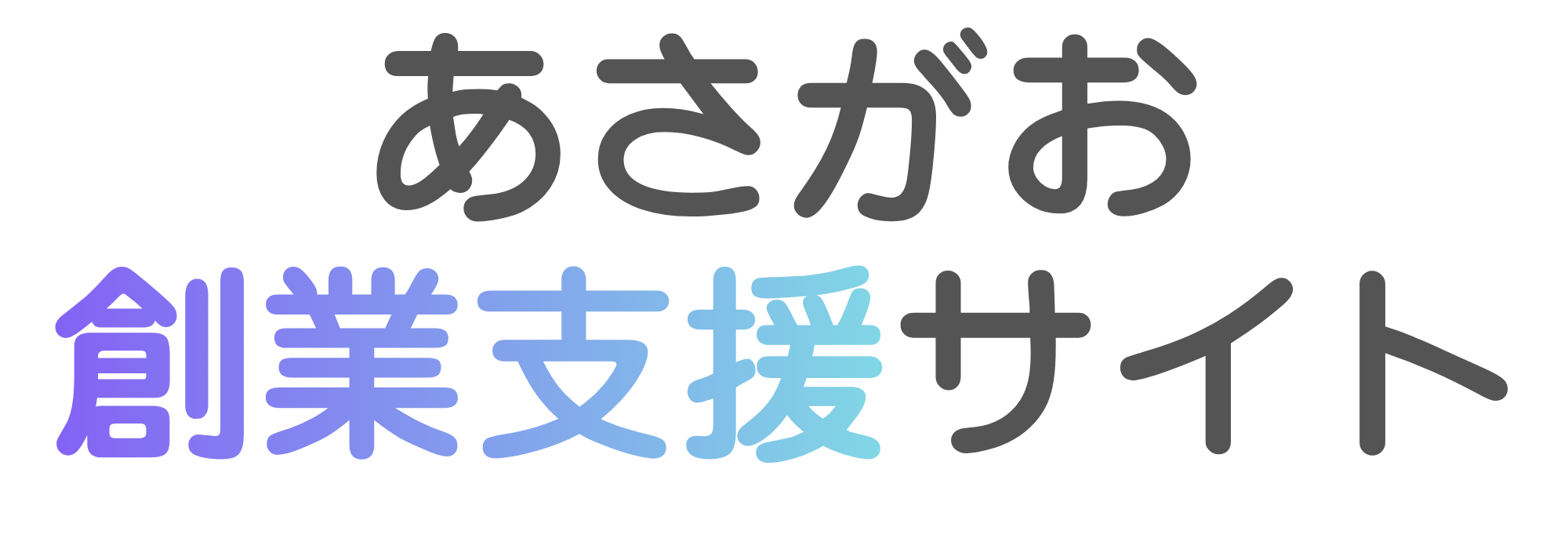
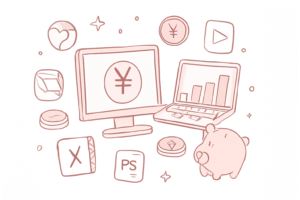
.jpg)